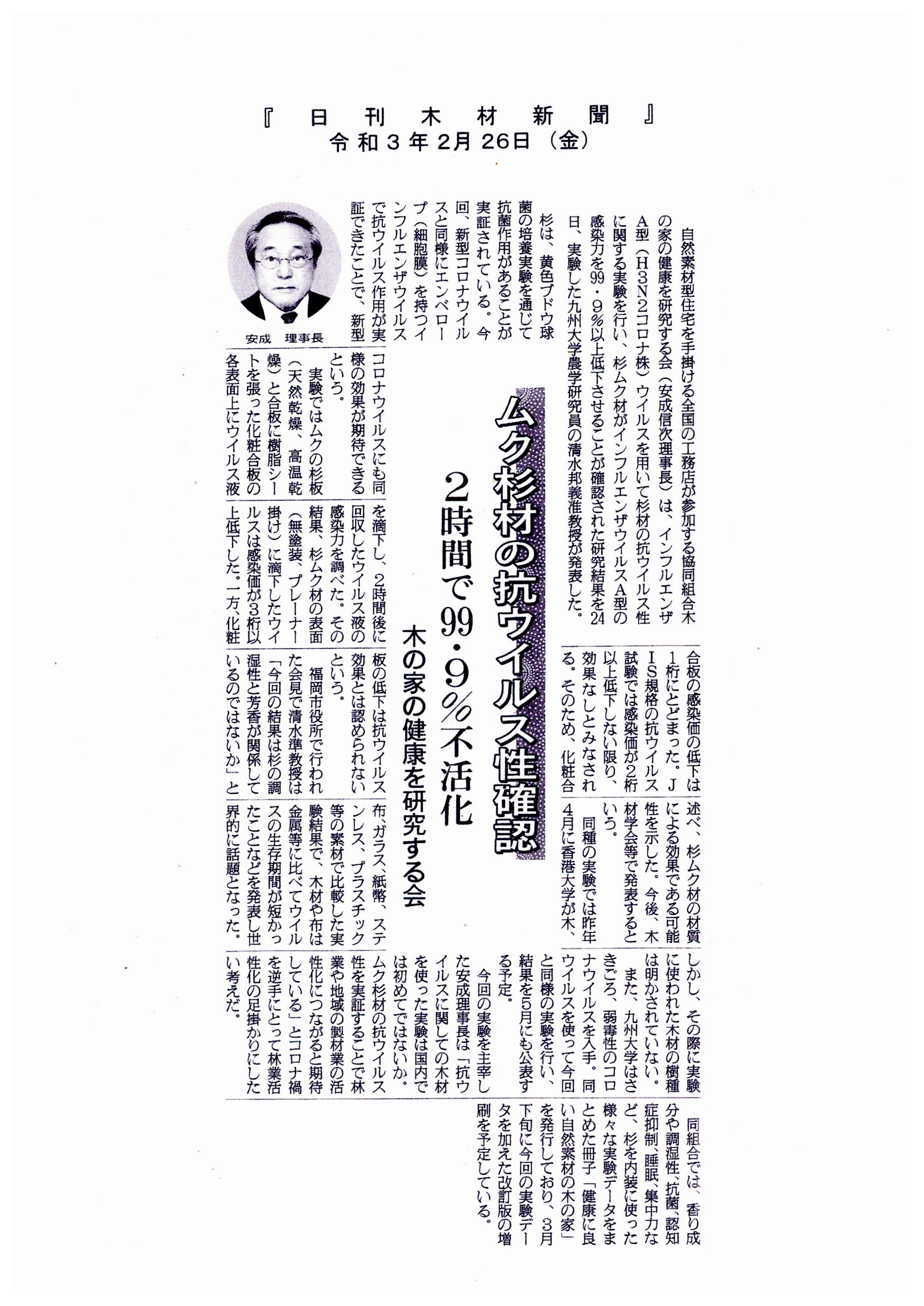百舌鳥の子育て
毎年6月には我が家の庭で、モズが子育てを行います。なぜか我が家に燕は寄り付きませんが、その代わりモズが巣をつくり子育てをしています。

写真は6月中旬の様子ですが、ヒナはかなり大きくなり小さな巣からはみ出しています。親鳥はつがいで忙しく餌を運んでいて、この数日後には巣立ちをしました。巣立ちをしてもヒナはうまく飛べないので、巣の近くの藪の中にいてまだ親から餌をもらっています。
人間や猫が巣に近づくと親鳥が「チチチチチチッ」とおおきな警戒音で鳴きます。この巣の場所は下の写真の我が家の玄関脇のマサキ生垣の中。昨年は、庭の木に作りましたが今年はまた一昨年と同様玄関の近くの生垣の中に作りました。

モズもツバメと同じで、天敵のヘビやカラスなどから巣を護るためには人間が生活行動している場所の近くのほうが安全と学習したのでしょう。
ツバメは近所の家の軒先などで子育てをしていますが、私の設計した家は、外壁がカラマツ板なので、どうもツバメに嫌われるようです。山の別荘でも、隣の杉の外壁にはキツツキが穴をあけるのに、私の設計した家のカラマツ外壁は何ともありません。カラマツの脂を鳥が嫌うのか、今までに鳥害を受けたことはありません。鳥に理由を聞いてみたいと思っていますが。
モズの子育てが終わると、毎年生垣の剪定を行います。