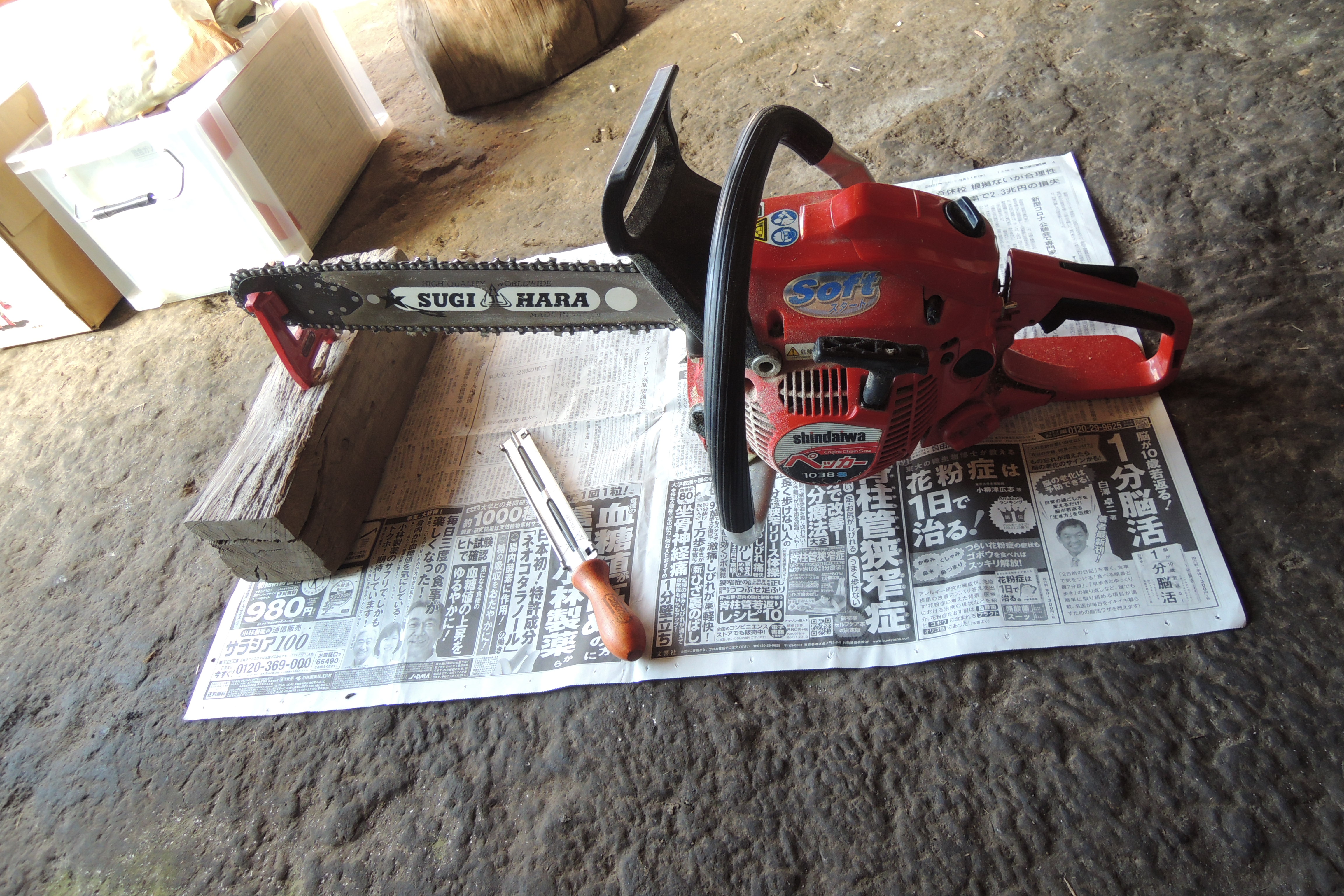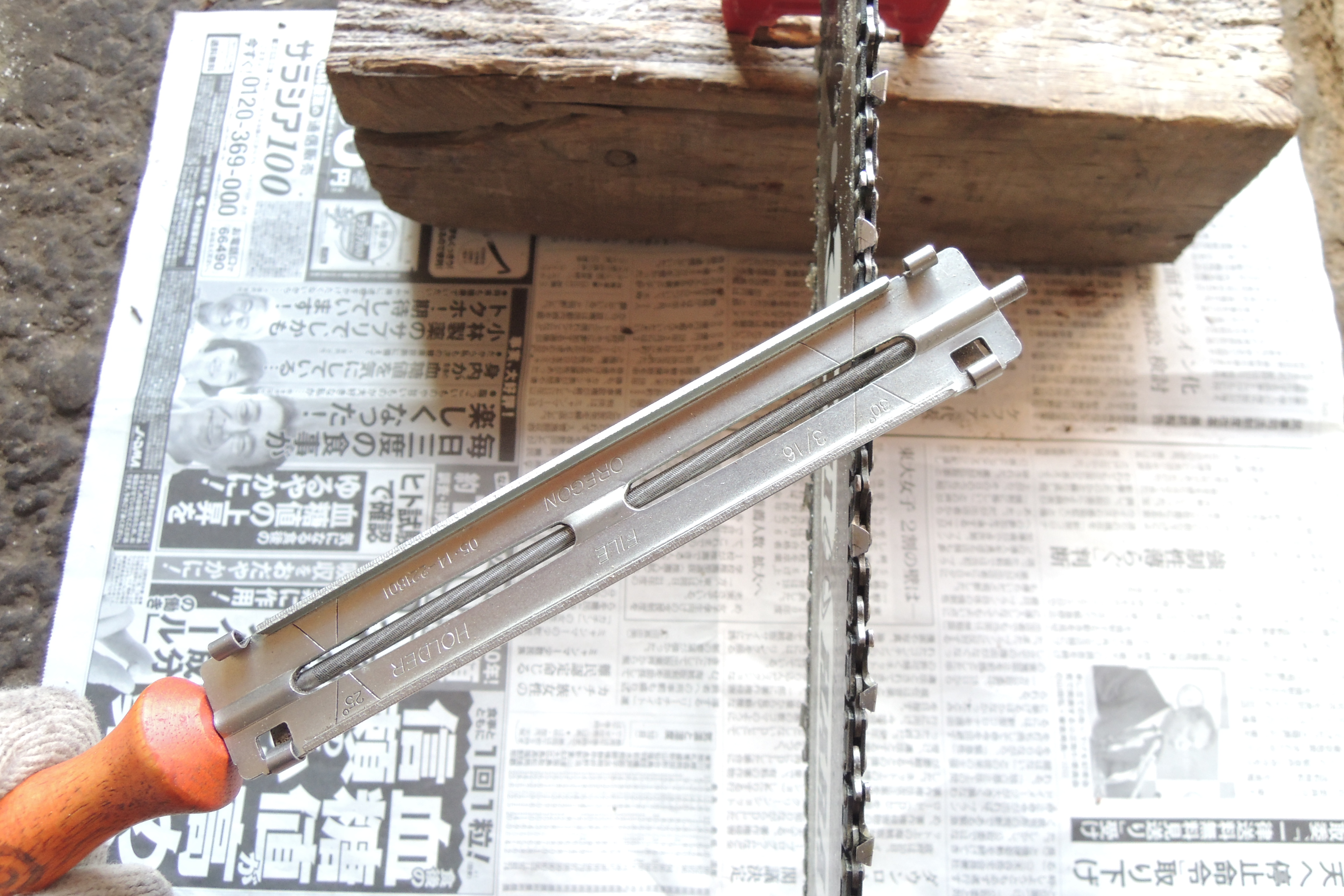2020年9月17日
今回は、板倉構法のルーツを探してみましょう。
 これは皆さん「校倉(あぜくら)造」としてご存じ の東大寺の正倉院です。奈良時代に建てられた、古代の美術工芸品の一大宝庫で、もちろん国宝、世界遺産でもあります。校倉造とは、三角形の校木(あぜぎ)という木材を井桁に積み重ねて外壁を造る構法で、写真の横ストライプの外壁でよく分かると思います。
これは皆さん「校倉(あぜくら)造」としてご存じ の東大寺の正倉院です。奈良時代に建てられた、古代の美術工芸品の一大宝庫で、もちろん国宝、世界遺産でもあります。校倉造とは、三角形の校木(あぜぎ)という木材を井桁に積み重ねて外壁を造る構法で、写真の横ストライプの外壁でよく分かると思います。
とても大きな建物で3つの部屋に分かれていて、向かって右から北倉(ほくそう)中倉、南倉と呼ばれています。よく見ると外観写真の真ん中部分(中倉)は、校倉造ではありません。中倉は厚板を柱の溝に沿って落とし込んだ「落し板倉構法」です。この中倉は後の時代の増築との説もありますが、部材の木材年代測定から北倉・南倉と同時期のものとの説が有力です。
有名な話に、正倉院の校倉の壁は湿度が低いときは校木(あぜぎ)が乾燥収縮し、隙間ができて風が通り室内を乾燥させる。湿度が高いときは校木が膨らんで湿気を遮断するので室内環境が安定し何百年も宝物を護ることができた、というものがありますがこれはちょっと違います。
無垢の木の外壁なので湿気を吸放出するのは確かなのですが、隙間ができて通気することはありません。宝物はさらに唐櫃(からびつ)というの無垢の木の箱の中で保存されたことが良かったようです。
校倉造も広義には板倉構法の一部ですが、「落し板倉構法」はこのように昔から大切な宝物を護る建物に使われてきました。このほか神聖な伊勢神宮も(形態は唯一神明造)壁は「落し板倉構法」です。

これは、私の地元上田市の塩田平にある中禅寺薬師堂です。平安時代末期に造られ重要文化財となっているもので、中部地方最古の建築といわれています。薬師如来坐像を納めた建物で、形態は阿弥陀堂形式一間四面堂といいますが、壁は「落とし板倉構法」です。

上が外壁写真で丸い柱に溝を突き、厚板を落とし込んでいるのがよく分かります。
この他、弥生時代の登呂遺跡や吉野ケ里遺跡などの穀物倉庫も高床の板倉構法によってつくられていたようです。このように板倉構法の堅牢性・耐久性、優れた温熱環境(断熱・調湿)性能は、古代から大切な穀物や宝物を護るために使われてきました。
古の知恵を賢く使い、機械に頼らず快適な住環境を実現するのが現代の「板倉の家」なのです。














 これは皆さん「校倉(あぜくら)造」としてご存じ の東大寺の正倉院です。奈良時代に建てられた、古代の美術工芸品の一大宝庫で、もちろん国宝、世界遺産でもあります。校倉造とは、三角形の校木(あぜぎ)という木材を井桁に積み重ねて外壁を造る構法で、写真の横ストライプの外壁でよく分かると思います。
これは皆さん「校倉(あぜくら)造」としてご存じ の東大寺の正倉院です。奈良時代に建てられた、古代の美術工芸品の一大宝庫で、もちろん国宝、世界遺産でもあります。校倉造とは、三角形の校木(あぜぎ)という木材を井桁に積み重ねて外壁を造る構法で、写真の横ストライプの外壁でよく分かると思います。